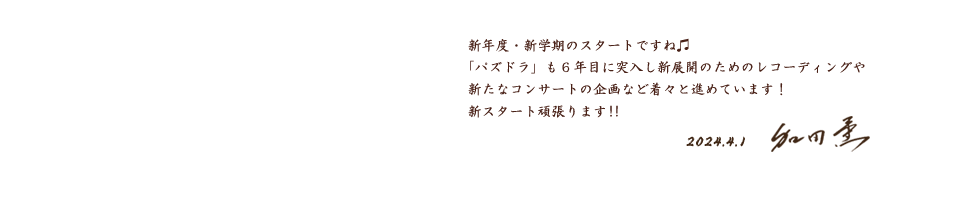Column 2010年「童謡詩劇うずら創作ノート」
童謡詩劇うずら創作ノート
カテゴリー
Vol.3 日本語とオペラ#3 日本語の歌考察
私は学生時代、モーツァルト作曲のオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の助演のアルバイトをしたことがある。歌うわけではなく、給仕や兵士など、セリフのない役どころを演じるのである。これが私のオペラ初体験なのだが、それはとても魅力的かつ創造的な現場であった。ただ、その公演は日本語訳詞による歌唱で、日本語でオペラを歌うことの居心地の悪さを同時に感じた瞬間でもあった。
日本語の歌で、しばしば問題として語られるのがアクセントの問題であろう。よく例に上げられるのが、山田耕筰の「赤とんぼ」である。歌い出しの「夕焼け子焼けの赤とんぼ」の部分の「赤とんぼ」のメロディーが、「あかとんぼ」と頭にアクセントがあるように聞こえ、実際の「あかとんぼ」と発音が違うという問題である。現在の研究では、発表当時の大正10年では、標準発音も「あかとんぼ」だったという研究発表がなされているが、注目は山田耕筰がメロディー創作に於いてアクセントをかなり重要視した点である。三木露風との共同作業による、日本語の歌のあり方を模索している様子が伺えるが、やはり山田がドイツ留学をした経験が最も大きいのではないかと思う。ドイツ語は、日本語よりアクセントに敏感で、また日常に於いても(演説などでも)アクセントの上手さが評価に繋がると言っても過言ではない。勿論、それはドイツの数多の大作曲家にも大いに反映されている。ドイツ留学を経て、その歌曲作曲法に影響されたことは想像に難くない。
しかし、日本語の特徴は決してアクセントだけの問題ではないのである。むしろ、地方によってはアクセントが逆になることも多々で、標準アクセントは明治時代の為政者の仕業であり、音楽はなんら影響を受けないと私は考える。勿論、日本語を美しく話す上でアクセントは重要だが、歌という観点からすると、むしろアクセントより「文脈」と「リズム」の方を重要視すべきではないかと思う。例えば、先の「赤とんぼ」でも、アクセントの問題は昔から言われているが、その曲が名曲であることは誰もが認めるところであるし、詩の内容がアクセントの位置によって損なわれるということもない。つまり、我々は歌を「単語」ではなく、「文脈」で感じているのである。
例えば、不自然に感じる歌は、歌詞を「夕焼け子焼け、の赤とーんぼ」など、文体を不自然に区切ったメロディー構成をしているのである。J-Pop系でメロディー優先という現状を鑑みれば、こういう現象も多く見られるのであるが、何か違和感を感じるのは、こうした文脈とメロディーとが整合されていないという問題点があるからである。
「リズム」に於ても同様で、4拍子や3拍子によるメロディー作曲法では、先のようにメロディー優先で不自然な文体割りが行われてしまうことがある。これとは対称なのが、デグラメーションという朗唱法である。ロシアの作曲家ムソルグスキーの作品の中に多く見られるが、所謂、言葉のリズムを優先し、5拍子や6拍子など、言葉に合わせたリズムを複合的に使った作曲法である。文体を切らずに文脈で歌を作る、この方法が日本語の歌にも有効なのではないかと考える。
和歌を披講する際、概ね同じようなリズムと抑揚(旋律感)で歌われるが、それは上記のアクセントやリズムの問題を超越した潜在意識による伝統の美観が働いているからである。しかし、ここにも日本語の歌を創作する際の重要なヒントが隠されていると考えている。五・七・五のリズム、2度音程や3度音程など限られた音程感での構成は、美意識を刺激しながらも、言葉の意味に意識を集中できるように築き上げられた技法なのである。
さて、これらの考察と童謡という観点からこの「うずら」の歌は作られた。どうしたら言葉の世界を歌で表現できるか? それは創作ノートVol.1でも述べたように「文学」と「音楽」は共存できるのかという大命題への挑戦でもある。
さらに、創作は手段として表現を伴うが、「歌い方」も大きな問題である。つまり、オペラといえばイタリアのベルカント唱法であるが、その唱法が決して日本語を歌う場合には適切ではないという問題である。
この問題は、実に奥が深く、私たちの文化意義に大きく関わってくるのである。