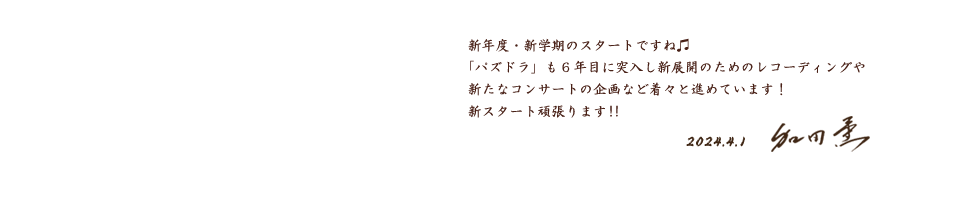Column 2010年「童謡詩劇うずら創作ノート」
童謡詩劇うずら創作ノート
カテゴリー
Vol.1 日本語とオペラ#1 日本語の歌とオペラ
2007年の秋頃、古くから親交があり私の作品の理解者である榑松さん(うずら公演実行委員会委員長/元東京フィル楽団長)から一本の電話を受けた。
「実は今、新作オペラの作曲者候補に和田さんの名前が挙がっているんだけど、どう?」
新作オペラ? ……うーん……
「すみません、オペラはちょっと… オペラは書いたことないし、まず日本語の“歌”を書くのが苦手で…」
という曖昧な言い方をしてお断りしようとした。
「いや、まだ候補だから。名前挙げるだけでもいいでしょ?」
「…名前だけなら…」
約3年間に渡る大きなプロジェクトの最初は、こんなやり取りで始まった。
作曲家にとって、作品の委嘱を受けるということは大変光栄なことであり、有り難いことである。しかし、オペラに関しては自分は未経験だし、委嘱を頂く資格はないと思ったのが正直なところ。何より「日本語の歌」の問題、そしてオペラという様式に対する私自身の未解決な問題があまりに大きかったので、むしろ避けて通りたい分野であった。
「日本語の歌」の問題。これは学生の頃からずっと自問してきた事なのだが、所謂“文学”と“音楽”の共存は可能かという命題である。何を今更、という御仁もおられようが、文学的呪縛に於いて音楽を支配されることが解決できないまま長年作曲活動をしてきた自身、純音楽における“歌曲”的なものはほとんど私の作品リストには無い。
例えば、校歌や映画やイベントなどで効用音楽としての“歌”はあるのだか、それは目的がハッキリしている。そしてアレンジャーとしても多くの“歌もの”を担当してきたが、その視点からも納得のいく「日本語の歌」の意味は得られなかった。
歌詩または歌詞とは、文学を更に抽象化し形而上学的な語感に洗練していくのだが、それを日本語の音楽としての様式化に自身が至っていなかったのであった。
それぞれの国には、それぞれの言語で“歌”は存在する。例えば、ベートーヴェンの第九の合唱は、文学的な名訳があるにせよ、やはり日本語で歌うと陳腐であり、意味は分からなくともドイツ語の語感の響きには敵わない。
私の作曲家としての信条は、日本の伝統的な音に共感し現代へ投企することなのだが、この日本の伝統的音楽のカタチと現代の文学(短歌や和歌でなく歌詞として)の共存に、まだ意義あるスタイルを見出せなかったのであった。
そして「オペラ」という様式、つまりヨーロッパ芸術の権化であるオペラが、自らの音楽的信条にどうしても相いれないのであった。オペラの歴史は、宗教音楽と同じくヨーロッパ音楽の根幹をなすもので、発生は16世紀末だが、文化的起源は紀元前のギリシャ時代にさかのぼる。つまり、その永々とした時の積み重ねの中に現在のオペラ芸術はある。
日本にも、能や歌舞伎のように文学・音楽・舞踊などの総合芸術としての舞台芸術はある。それらは、日本人の潜在意識の中に大きな価値観を形成していて、現代でも演劇や映画などあらゆるジャンルに継承されている。例えば、「寅さん」のような映画は日本人にしか作れないし、未だに忠臣蔵に共感する人は多い。
しかし、オペラに限って言えば、日本の現代オペラはヨーロッパのそれの借り物に過ぎないのではないと、ずっと感じていたのである。勿論、日本の歴史や音素材を使った日本風オペラも存在するが、それは果たして歴史の継承者となるのであろうか?その疑問が悶々と長年私の中にあった。
これら大きな二つの問題が、榑松さんからの電話で咄嗟によぎったのであった。だから最初は全く消極的であったし、お断りするつもりだったのだが…
数日後、
「和田さんで決まったよ。」と、榑松さんからの電話。
「えええ! 僕ですか?! 他に適任者が入るでしょう?」
「いや、実行委員会の多数決で決まったんだよ。お願いしますね。」
「いやいや、ムリですよ。オペラ書いたことなし…」
「書いたことない人がいいんだって。お願い、頼みますよ。」
ここから3年間の格闘の日々が始まった。